新着情報 / お知らせ



2月になりました!
みなさんの中にも、大事なテストを近くひかえている方は多いでしょう。
入学試験に学年末テストなど、自身の最高の結果を出せるように当日まで気を抜かず一緒に頑張りましょう!
もちろん、勉強の面に限らず健康管理も非常に大切です。
体調を崩さないようにするために、難しいことをする必要はありません。
「栄養をしっかりとる」
「休息をしっかりとる」
この二つを、いつも以上に心掛けるようにしてくださいね。
例えば勉強中に疲れを感じたら、お菓子をつまむのも良いでしょう。
「糖分」も立派な栄養です。
入試の会場にも可能であれば、チョコレート菓子などを休み時間に食べるために持っていくと良いですね!
試験のコツを教えます!関塾の無料体験授業はこちらから!
今の時期は丁度、コンビニなどのお店でも大きくチョコレートが取り上げられているのを目にしますね!
家で作ったことがある方も多いのではないでしょうか。
甘いチョコレートにはもちろんブドウ糖が多く含まれているので脳の栄養補給には最適ですが、それ以外にもカカオ豆由来の勉強に役立つ成分が含まれていますよ!
まず、カカオポリフェノールには脳内の記憶に関わる物質を活性化させる作用があります。
それからテオブロミンにはリラックス効果、緊張を抑える効果が期待できます。
ただし、これらの成分はホワイトチョコレートには含まれていないか、含まれる量が少ないことがあります。
チョコレートを勉強目的で買う時は「カカオマス(あるいはカカオパウダー)」が材料にあるか、チェックしましょう。
ちなみにカカオは、中央アメリカから南アメリカが原産の植物です。
歴史を調べればなんと約2000年前からアメリカ先住民族はカカオを栽培し、食料や薬として口にしていたようです。
チョコレートの語源も、スペイン人やポルトガル人がアメリカ大陸にやってきた時に先住民族がカカオ豆からできた飲料を「ショコラトール」と呼んでいたことに由来する説が有力です。
ただ、その飲料は粉末にしたカカオ豆を水に溶いて唐辛子を加えたものだったそうです!
これはレシピの一例ですが、当時のショコラトールは今のココアとは全く異なる味わいになりそうです。
ショコラトールも「苦い(酸っぱい)水」という意味らしく、苦味や酸味を楽しむのがアメリカ先住民族の好みだったのかも知れませんね。
この記事は、いい休憩になりましたか?
もうすぐ進級、進学の時期です。
1日1日を大切にして、集中して勉強しましょう。
Dr.関塾 中原校です。
昨年は大変お世話になり、講師一同心より御礼申し上げます。
さて、2026年が始まりましたね。
受験生の皆さんは本番まであと少し!
例年インフルエンザが猛威を振るう時期です。
マスクを着ける、部屋の加湿をするなど予防を昨年以上に行って、万全の体調で試験日を迎えましょう!
今、受験生でない皆さんも気づけばもうすぐ新学年です。
今年の目標はもう決めてありますか?
これからの一年間、不安なことがあれば何でも先生たちに聞いてくださいね。
今年も皆さんを全力でサポートします。一緒にがんばりましょう!
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
本年も宜しくお願い申し上げます。みんなで良い1年にしていきましょう!!
※無料の冬期講習会、まだ間に合います。
春にスタートダッシュを決めるための燃料を、冬のうちに充填します。
お友達と一緒に関塾でがんばろう!
★お問合せはこちら★

年末年始のため以下の期間は休校になります!
★12月29日(月)~1月3日(土)
※なお、教室によって休校日が異なる場合があります!
詳細は教室へお問い合わせください。
2026年もよろしくお願いします!
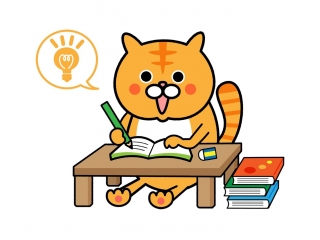
こんにちは!Dr.関塾 中原校です。
もうすぐ2学期が終了します!
受験生の皆さんは本番まであと少しですね!
年末年始は少しだけ一休みして良いですが、最後まで気を抜かないようにしましょう!
家でも塾でもよく頑張っていると思いますが、健康面の注意も怠ってはいけませんよ。
部屋が寒いと風邪を引くかも知れませんし、そうでなくても集中が妨げられてしまいます。
足やお腹をあったかくさせておくことを意識しましょう。
頭は逆に暖かくしておくと、眠気を誘発することがあります。
部屋を暖かくして、額には熱さましの冷却シートを貼るのもおすすめです!
そして今受験生でない皆さんも、もうすぐ新学年です。
2026年最初の勉強を始める時は、今年12月に学んだことや取り組んだことを科目ごとに復習してみましょう!
どれだけしっかり覚えようとしても、数日休んだら何かしら忘れてしまうものです。
教科書を見ながら「関塾の先生にこれを聞こう!」と、質問する問題を決めておくのも良いですね!
改めて、これからの一年間不安なことがあれば何でも先生たちに聞いてくださいね。
今年も皆さんを全力でサポートします。一緒にがんばりましょう!

みなさんこんにちは!
関塾の冬期講習会が今年も始まりました!
すでに情熱に燃えている方はもちろんのこと、2学期に成績を落としてしまった方 今年の目標を果たせなかった方 勉強なんかやっても無駄だと思っている方も大歓迎です。
来年こそみなさんの輝く時になるように、全力で指導します!
冬期講習会の内容は本人様と保護者様のご要望を伺った上で提案させていただきます!
自身の目標や課題は、みなさんの中でも様々であると思います。
それぞれの目的のために、ぜひ冬期講習会の参加をお待ちしております!
例えば学年末テストの対策であったり
英検・数検・漢検対策でも構いません。
今年できてしまった苦手分野の克服であったり
来年を見据えて勉強習慣の確立でも良いでしょう!
みなさんのご要望を、お聞かせください。
ホームページからのお問合せはこちらです!
行事日 : 2025年10月27日

三鷹五中と六中のテスト点数UP例です!
皆さん頑張りました!

みなさんは、毎日勉強していますか?
「練習する習慣」や「読書する習慣」など、何か習慣を取り入れようとするのは非常に難しいことだと感じます。
実際にやろうとして失敗した方は分かると思いますが、途中で続かなくなってしまうのですね。
「三日坊主」という言葉を聞いたことがある方も、多いでしょう。
これは飽きっぽくて物事が続かないことを意味しています。
今日は「毎日勉強するために必要なこと」を紹介します。
先生たちも継続できたり失敗したことがありますし、ダイエットなど物事を長く続けるための研究は世界中で行われています。
そこからみなさんに取り入れて欲しいことを、三つお話しします。
ぜひ読んでみてください。
①環境をつくる
「集中できなかった」時のことを逆に考えてみてください。
勉強中にスマートフォンの通知が気になったりしていませんか?
机の上にはその日の勉強に必要なものだけがある状態にしましょう。
ご家庭で環境を整えるのが難しいなら、関塾に自習に来ると良いですよ!
いつでも先生に聞ける!関塾の無料体験授業はこちらから!
②小さな目標をつくる
「学年末テストで100点をとる」という目標は、その日勉強する意欲には結びつきません。
普段勉強する習慣がない人ほど、すぐに達成できる小さな目標から始めましょう。
例えば「例題を2つ書き写す」とか「単語を3つ覚える」などです。
勉強量を増やすかどうかは、習慣が身についてから考えても遅くはありません!
③既にある習慣につなげる
最初は5分、10分の勉強時間から始めるとしても、いつ勉強するかは迷うところです。
10分の勉強も、後回しにし続けた結果やらずに寝てしまった、ということも起こるかも知れません。
その対策として、今の習慣に関連付けて勉強するタイミングを決めると良いですよ!
「お風呂から上がったら、単語帳を開く」
「塾の授業が終わったら、1ページ問題を解き進めてから帰る」などが良い例です。
これから冬休み、そして新年を迎える今の時期は、新しい習慣を身につけるのに丁度良い時期です。
困っていることや、うまくいかないことがあればぜひ、先生に聞いてみてくださいね!

こんにちは!中原校です!
普段勉強していない人が、試験などの前夜に徹夜で勉強することを「一夜漬け」といいます。
みなさんは、したことがありますか?
徹夜が人間の健康に良くない影響を及ぼすことは、みなさんもよく分かっていると思います。
ただ、昔も今も中高生は毎日忙しいものです。
今こうして生徒の進路指導や勉強法を教えている先生たちも、もちろん全てのテストを準備万端で迎えてきた訳ではありません。
興味があれば身近な先生に一夜漬けについてを聞いてみましょう。
きっと、色々な失敗談を教えてくれるはずです。
関塾の個別指導では、生徒が楽しんで勉強できる環境づくりを意識しています。
いつでも質問できる!関塾の無料体験授業はこちらから!
ですから今回の記事は、頭ごなしに「一夜漬けはダメ」と注意する内容ではありません。
テスト前夜に語句・公式などが覚えられていなければ、どうするべきか、一緒に考えましょう。
まず行うべきは、勉強する内容を厳選することです。
前提として明日のテストでうまく行く可能性が低いのですから、応用問題や解くのに時間のかかる問題、歴史の年号のように直接出題される可能性の低いものは翌朝に回してください。
国語なら漢字や古文用語などの語句、動詞の活用など表で出題されやすいものの暗記が前夜の勉強には適切です。
理科や社会も、教科書で図表になっている部分は、テスト当日の穴埋め問題に対応できるようにしっかり勉強しましょう。
英語はもちろん単語の暗記、それから確実に出題される教科書本文の書き取り練習も効果的と言えます。
数学は公式を覚えるか、公式を覚えるだけで解ける基本問題を練習すると良いでしょう。
どの科目にも共通していることですが、確実に覚えるという意味でも、途中で寝てしまわないようにという意味でも、見るだけで済ませるのではなく書いて練習しましょうね!
それから、テストで点数を取りたいのならばやはり睡眠時間は必要です。
1時間ぐらいあれば良いという話でもありません。普段と同じ時間に寝て、普段と同じ時間に起きるのが結局ベストと言えます。
朝まで勉強しようとしても、人間はあまり長く集中力を保てる訳ではありません。
むしろ、就寝時間までに勉強を終わらせることを考えて、計画的に取り組みましょう。
そうしてみると、忙しくても毎日勉強する習慣は必要であると思えるはずです!

いつもご覧いただきありがとうございます。関塾中原校です。
夏真っ盛り!夏休みは学校の宿題、塾の夏期講習など勉強の予定のほかに
BBQやキャンプ、家族で旅行など遊びに行く予定が入っている人もいると
思います!はたまた外は暑すぎるので映画館など涼しいところもいいですね~
長期間のお休みを計画的に楽しみましょう!
ところで関塾もこの時期、特別なお休み期間があるのでお知らせします!
◎休校期間:8月12日(火)~8月15日(金) の4日間
◎授業開始:8月16日(土)
しっかりリフレッシュして、休み明けからまた勉強を一緒に頑張っていきましょう!